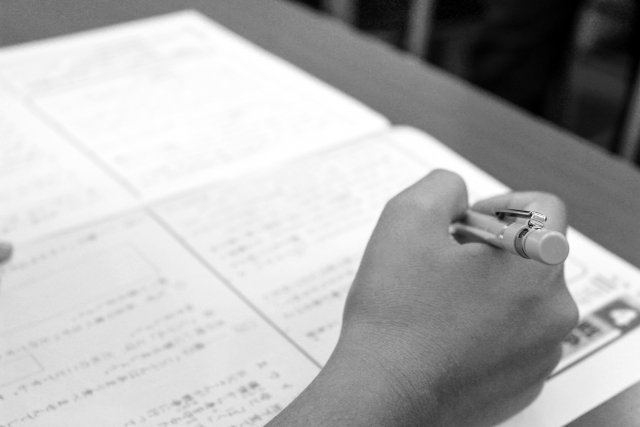勉強しているのに、なかなか成績が上がらない。ワークを3周解いたのに、テスト本番では思うような点数が取れない。
そんな悩みを抱えている中学生・高校生は少なくありません。
実は、そういう生徒に共通しているのが、**「受け身の勉強」**にとどまっていること。
ワークや問題集を解くだけでは、知識は「確認」できても、「定着」や「活用」にはつながりにくいのです。
そこで今回は、成績アップを本気で目指す人にこそ実践してほしい、**究極の勉強法『テスト予想問題作成勉強法』**をご紹介します。
「テスト予想問題作成勉強法」とは?
その名の通り、自分で「先生が出しそうな問題」を予想して、自分で問題を作る勉強法です。
一見遠回りに見えますが、実はこの方法には次のような効果があります。
✅ 教科書やノートの内容を深く読み込むようになる
✅ 出題の傾向や先生のクセに敏感になる
✅ インプットだけでなく「アウトプット力」が養われる
✅ 「出す側の視点」で考えるため、記憶の定着率が飛躍的に上がる
たとえば、社会の授業で「日清戦争」がテーマだったとしましょう。
ワークを解くだけでは、「年号」「条約の名前」「戦争の結果」を覚える程度かもしれませんが、予想問題を作る場合はこう考えるはずです。
- この内容で記述問題を出すならどうなる?
- 教科書の太字をどう使う?
- 年号を使った並び替え問題は作れる?
こうした視点で学習することで、自然と内容の本質が見えてきます。
実践手順:どうやって取り組めばいい?
STEP1:出題範囲を把握する
まずは、定期テストの出題範囲をしっかり把握しましょう。配られたプリントや学校の先生の発言を要チェック。
STEP2:教科書・ノート・ワークを分析
出題範囲の内容を、教科書・ノート・ワークなどを使って徹底的に読み込みます。
- 教科書の太字・図・表・資料
- ノートの板書・補足説明・先生のコメント
- ワークで繰り返し出てくるパターン問題
これらを眺めながら、「もし自分が先生だったら、どこを問題にするか?」を考えます。
STEP3:予想問題を作る
いよいよ問題作成です。
- 穴埋め問題
- 記述式問題
- 選択肢から選ぶ問題
- 並べ替え問題
- 資料から読み取る問題
できれば、各単元ごとに1〜3問ずつ作ってみましょう。理科・社会はもちろん、国語(漢字・文法)、英語(文法・語順)、数学(文章題の設定)にも応用できます。
STEP4:自分で解いてみる/友達と交換する
作った予想問題を自分で解く→答え合わせするという流れが、復習に最適です。 さらに効果的なのが、友達と問題を交換し合って解くこと。
自分とは違う視点で作られた問題に触れることで、知識の抜けや新たな気づきを得ることができます。
成績上位者は「先生の気持ち」で勉強している
「この先生は、必ず授業中に強調したところから出す」 「去年のテストを見ると、図を描かせる問題が必ず1問は出てる」
実は、成績上位の生徒たちは、このように**「出題者の視点」でテスト対策をしている**のです。
これは偶然ではありません。
問題作成者(=先生)の立場に立ってみると、
- どの知識を理解していてほしいか?
- どの観点で思考力を試したいか?
- どこを取りこぼしやすいか?
といったことが見えてくるようになります。
「問題を作ること」自体が、最強の理解トレーニングなのです。
まとめ:最強の受け身脱却法、それが「予想問題作り」
テストで結果を出すためには、ただ暗記して終わりではなく、「使える知識」にまで高める必要があります。
そのために有効なのが、予想問題を自分で作ること=学びをアウトプットすること。
これは一朝一夕でできることではありませんが、習慣化すればするほど、驚くほど深い理解と記憶が手に入ります。
ワークを3周やるよりも、1回自分で予想問題を作ってみる。それだけで、勉強の質が一気に上がるはずです。
さあ、次のテスト対策は「問題を作る」ことから始めてみませんか?
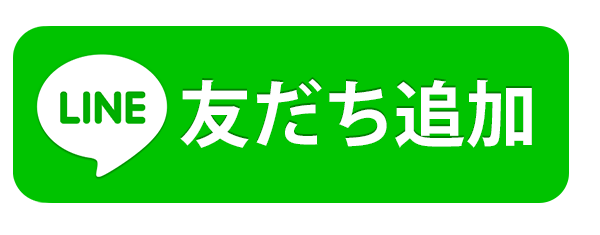
個別指導塾 「s-Live(エスライブ)かながわ北山田駅前校