「まだ高校1年生だし、受験はまだ先の話でしょ?」
そう思っている人、実はとても危険です。
ここ数年で、大学入試の状況は大きく変わりました。かつては「早慶を目指して、ダメならMARCHで」という進路の流れが一般的でした。しかし、今やその「MARCHに入ることすら難しい時代」になっているのです。

◆ 一般受験の門戸は確実に狭くなっている
まず知ってほしいのは、一般入試の定員が大幅に減っているという現実です。
文部科学省が進めてきた「定員厳格化」により、私立大学は合格者数を減らしています。
特に人気大学では、合格倍率が以前の倍近くに跳ね上がりました。
例えば、早稲田や慶應では、わずかな得点差で大きく合否が分かれます。
「あと1問できていれば」「あと数点取れていれば」という世界です。
MARCH(明治・青山・立教・中央・法政)ですら、共通テスト利用で高得点を取らなければ受かりません。
つまり、“安全校”だったはずのMARCHが、今では“実力校”になっているのです。
◆ 「高2からでいいや」は通用しない
「本気を出すのは高2からで十分」——これは、ひと昔前の常識です。
今は高1からの学習量で、すでに差がついています。
高2で理社が本格化し、高3で過去問演習に入ることを考えると、英語・数学・国語の基礎を高1で固めておくことが、合格の絶対条件になっています。
早慶・MARCHを受ける受験生の多くは、
- 高1のうちに英単語3000語以上を覚え、
- 文法を一通り終え、
- 数ⅠA・ⅡBをある程度理解している
という状態です。
「まだ高1だから」と油断していると、半年後には取り返しのつかない差がついてしまいます。
◆ 推薦・総合選抜の比重が増えている=評定が命
もうひとつの変化は、推薦・総合型選抜の枠が増えていること。
国の方針として、大学入試全体の約半数がこれらの方式で合格しています。
つまり、定期テストで評定平均を高く保っていれば、早慶やMARCHの指定校推薦、あるいは総合選抜でチャンスをつかめる可能性があるということです。
逆に、「テスト勉強は面倒だから」とサボってしまうと、推薦ルートは完全に閉ざされます。
評定平均4.3〜4.5以上があれば、難関大学の指定校推薦の切符を手に入れるチャンスがあります。
しかし、その土台はまさに高1の最初の定期テストから始まっているのです。
◆ 共通テスト重視の時代、基礎が全てを決める
共通テストでは、思考力を問う問題が増えていますが、結局は「基礎が完璧であること」が前提です。
英単語を覚えきれていない、公式があいまい——そんな状態では、いくら応用問題を練習しても点は取れません。
高1の段階で英語と数学の基礎を盤石にしておけば、共通テスト対策にも直結します。
「高校の勉強=受験勉強」だと意識することが、合格への最短ルートです。
◆ 今、本気になった人が2年後に笑う

早慶を目指すなら、高1の今がスタートライン。
「まだ大丈夫」と思っているうちは、すでに周囲が先に走り始めています。
1日30分でもいい。
英単語を覚える、授業を復習する、苦手を放置しない——その小さな積み重ねが、後々とてつもない差になります。
逆に、今を逃せば、高2の夏には「基礎をやり直す時間」しか残っていないかもしれません。
◆ 焦ることは悪くない。行動すれば“武器”になる。
「焦る」という感情は、決してネガティブなものではありません。
それは“気づけた人だけが感じるサイン”です。
焦りを行動に変えられる人が、最終的に合格を勝ち取ります。
もし、「何から始めればいいかわからない」「自分の勉強法が合っているのか不安」と感じているなら、S-Liveかながわ北山田駅前校を訪れてみてください。
S-Liveでは、東大生講師による質問対応や、基礎を徹底的に固めるカリキュラムで、高1生の段階から“受験で勝てる力”を育てます。
受験が本格化する前の今こそ、差をつける最大のチャンスです。
「まだ高校1年生だから」ではなく、
「高校1年生のうちにできることを全部やる」。
その意識が、あなたを早慶合格へと導きます。
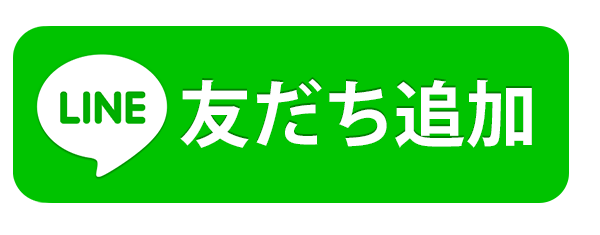
個別指導塾 「s-Live(エスライブ)かながわ北山田駅前校



