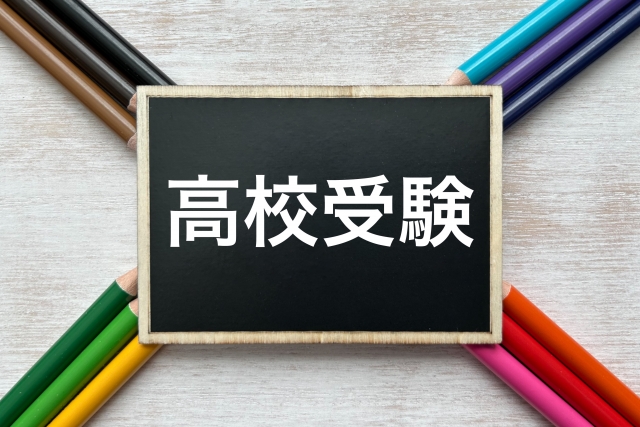~接続語・指示語・選択肢に注目すれば正解が見える~
高校入試の国語では、「説明文」の読解が必ずといっていいほど出題されます。筆者の主張や話の展開を的確に読み取る力が試される問題ですが、実はコツさえつかめば、誰でも正解に近づくことができます。
今回はそのためのポイントを、次の3つに絞ってお伝えします。
✅ ポイント①:接続語の役割を確認する
説明文では、「しかし」「つまり」「たとえば」などの接続語が、話の流れをつかむカギになります。特に注意したいのは、「逆接」(しかし、ところが)や「言い換え・要約」(つまり、要するに)です。
これらの接続語は、筆者の意見が出てくる場所を教えてくれたり、具体例の前後を示してくれたりします。
「接続語の直後」に重要な内容がくることが多いので、マークをつけて読み進めましょう。
✅ ポイント②:指示語が何を指しているか確認する
説明文には「これ」「それ」「このような」「そうした」などの指示語が多く使われます。
曖昧に読んでしまうと、文章全体のつながりが見えなくなってしまいます。
指示語を見つけたら、「それは何を指しているのか?」を、必ず立ち止まって確認しましょう。コツは、「直前の文を読み返す」ことです。多くの場合、直前にある内容や言い換えが指されています。
✅ ポイント③:選択肢は「消去法」で切っていく
選択肢問題を解くときにやってしまいがちなのが、「何となく正しそう」で選んでしまうことです。
正解を選ぶというよりも、「明らかに間違っている選択肢を切っていく」方が正答率は上がります。
・本文に書いていないことを言っている
・言い換えになっていない
・細かいところが本文と違う(主語が変わっている、言いすぎている)
などの特徴に気づければ、確実に選択肢を減らせます。
✍ オリジナル例題(説明文)と設問で実践!
文章を読んで、問いに答えなさい。
【本文】
人間の脳は、「変化」を強く意識するようにできています。たとえば、ずっと同じ音が流れていると、その音にだんだん気づかなくなってしまいます。しかし、突然別の音が聞こえると、たちまち注意を向けます。このようなしくみは、私たちが環境の変化にすばやく反応できるようにするために進化してきたと考えられています。
つまり、人間は「慣れ」によって、変化しないものには注意を向けなくなるのです。これは集中力が低いということではなく、脳が効率よく働いている証拠です。
このように、脳は「同じ状態が続くと、それを無視する」ようになっています。だからこそ、集中力を長く保つには、適度な変化を取り入れることが必要なのです。
【問1】
「しかし、突然別の音が聞こえると、たちまち注意を向けます。」の「しかし」は、どのような関係を表していますか。
A. 原因と結果
B. 順接(だから)
C. 逆接(反対の内容)
D. 補足(説明の追加)
【問2】
「このようなしくみ」とは、どの内容を指していますか。
A. 音に対する集中力が高いこと
B. 音の変化に反応する脳のはたらき
C. 環境の音をすべて聞き分ける能力
D. 静かな場所で勉強に集中できること
【問3】
本文の内容に最も合っているものを選びなさい。
A. 脳は常にすべての情報に集中している。
B. 脳が慣れることは集中力が弱まっていることを意味する。
C. 同じ状態が続くと、脳はそれを無視する傾向がある。
D. 音の変化が多いと、脳は混乱してしまう。
【解説と解き方のポイント】
▶ 問1:接続語に注目
「しかし」は、前の文との逆接を表しています。
→ 前:「ずっと同じ音」→「気づかなくなる」
→ 後:「突然別の音」→「注意を向ける」
⇒ 反対の内容なので、正解:C
▶ 問2:指示語に注目
「このようなしくみ」の「しくみ」は、どんな仕組み?
直前にあるのは、「変化に注意が向く脳のはたらき」
⇒ 正解:B
▶ 問3:選択肢の切り方
A →「常にすべてに集中」→ ✕ 書いてない
B →「集中力が弱まっている」→ ✕ 否定されている
C →「同じ状態が続くと、無視する」→ 〇 本文通り
D →「混乱してしまう」→ ✕ 書かれていない
⇒ 正解:C
🌟 まとめ
説明文の問題を解くときは、「何となく」で読むのではなく、次の3つに必ず注目しましょう。
✅① 接続語
→ 文の流れ、筆者の意見を読み取るヒントになる
✅② 指示語
→ 何を指しているかを特定すれば、内容理解が深まる
✅③ 選択肢の切り方
→ 消去法で「明らかに違う」ものから削っていくのが正解への近道!
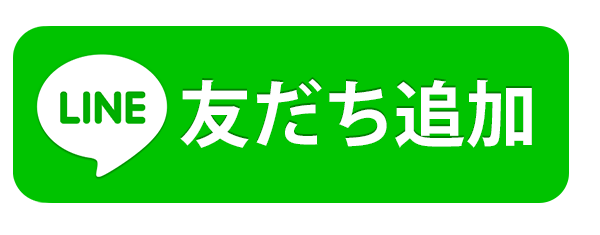
個別指導塾 「s-Live(エスライブ)かながわ北山田駅前校