未来の働き方を生き抜くために、ご家庭でできること
AIやテクノロジーが急速に進化し、10年後には今の仕事の半分が変わるとも言われています。
そんな時代を生きていく子どもたちに、本当に必要なのは「いい学校に入ること」や「偏差値の高い勉強」だけではありません。
それよりもずっと大切なのが、社会でたくましく生きるための**“3つの力”**です。
それは――
① 自分で学び、自分で動く力
② チームで成果を出す力
③ 小さく始める力
この3つの力は、将来どんな仕事に就いても、必ず役に立ちます。
では、どうすれば子どものうちから育てていけるのでしょうか。
家庭でできること、そして第三者の力を借りる方法を一緒に見ていきましょう。
① 自分で学び、自分で動く力
今の時代、「誰かに言われてから動く」だけでは生き残れません。
社会では、“自分で課題を見つけ、学び、行動する力”が求められています。
小学生や中学生のうちは、「自分で考える習慣」を持つことが第一歩です。
▽ 家庭でできること
たとえば、宿題をする順番を親が決めるのではなく、
「今日はどれからやる?」と子どもに任せてみる。
失敗しても、「だからダメでしょ」ではなく、「次はどうしようか?」と問いかけてあげる。
また、家の中でも“任務”を与えるのが効果的です。
「夕食のサラダをお願い」「お風呂掃除はあなたの担当」など、小さな責任を持たせることで、“自分で動く習慣”が自然と身につきます。
▽ 第三者に任せるなら
- 探究学習やプログラミング教室など、「自分で考えて試す」タイプの学び
- 好奇心を刺激してくれる体験型イベント
こうした場で、「正解のない問題」に挑戦する経験が、“自ら動く力”を強く育てます。
② チームで成果を出す力
どんなに優秀な人でも、ひとりでは大きな成果は出せません。
これからの社会では、「チームで協力しながら成果を出せる人」が重宝されます。
学校でも部活でも、まずは“他人と違ってもいい”と認め合うところから始まります。
▽ 家庭でできること
家族をひとつのチームとして考えてみましょう。
たとえば、週末の夕食を「家族で一緒に作るプロジェクト」にする。
一緒にメニューを考え、買い物をして、片づけまで分担する。
その中で、意見がぶつかったときには「どうすれば全員が納得できるかな?」と話し合う練習をします。
そして何より大切なのは、親自身が“チームメイト”として関わる姿勢です。
「ありがとう」「ごめんね」を素直に言える親の姿を見せるだけで、子どもは“協働する姿勢”を自然に学んでいきます。
▽ 第三者に任せるなら
- スポーツチーム、吹奏楽、合唱などの「チームでの挑戦」
- 地域ボランティア活動など、異年齢での協働体験
人と関わりながら「一緒に何かを成し遂げる」経験こそが、社会で通用する“チーム力”を育てます。
③ 小さく始める力
何かを始めるとき、「うまくできるか」「失敗したらどうしよう」と考えてしまうのは、大人も子どもも同じです。
けれど、本当に大切なのは**“とりあえずやってみる”**という一歩。
完璧を求めずに、小さく始めて、続けてみること。
それが、未来を切り拓く力になります。
▽ 家庭でできること
「やってみたい!」という気持ちが出たら、できるだけ止めずに背中を押してあげましょう。
「じゃあ一週間だけやってみようか」「試しに少しやってみよう」で十分です。
そして、結果よりも「行動したこと」自体をしっかりほめること。
「チャレンジしてえらかったね」「まず動けたのがすごいね」――
この言葉が、次の行動への原動力になります。
今日学校で習ってきたこと一つ教えて?とアウトプットする機会を毎日作る
▽ 第三者に任せるなら
- 発表型の塾やスピーチ教室など、「アウトプットする場」
- 地域の子どもイベントで、販売や企画を体験する活動
▽ 自分でできること
- 1日1長文500単語の文章を読むと
- 少なくとも500単語は単語に触れる
- わかる単語が数百語それだけで増える
自分で考え、行動し、発表する――そんな小さな成功体験が、“挑戦できる心”を育てていきます。
おわりに
これからの時代に必要なのは、テストの点数よりも“生きる力”。
そしてその力は、日常の中で確実に育てることができます。
「自分で考える」「人と協力する」「まずやってみる」
――たったこれだけの習慣が、10年後、社会で光る力になるのです。
お子さんが未来に迷わず、自分らしい働き方を見つけられるように。
今日から、ほんの少しずつ、“3つの力”を育てる時間を意識してみませんか。
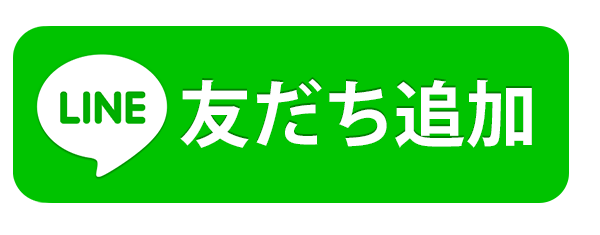
個別指導塾 「s-Live(エスライブ)かながわ北山田駅前校



